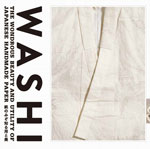
お椀も箪笥も着物も、みんな和紙でできていた!
明治に入るまで和紙は、農閑期に庶民が漉く手軽な素材であり、様々に代用可能な優れた生活用材だった。漉き方や産地によって特長のある和紙に、揉む・張る・撚る・編むなどの多様な加工を加え、工芸品のような暮らしを彩る道具が作られてきた。
本書では、木、布、皮などに擬態した変幻自在な紙製品、約70点を「衣」「食」「住」「遊」の生活場面からカラー図版で紹介。和紙文化が栄えた江戸時代から昭和初期にかけ、丹精を込めて生み出された逸品を披露する。巻頭では繊維の不思議を解き明かし、巻末で未来に繋がる和紙の素材力と魅力を語る。さまざまな造形を生んだ和紙の可能性をみつめた一冊。
■目次
□和紙のちから
柔らかな光を通す/水を吸う/水をはじく/軽くて強い/開閉自在/繊維を操る/糸状にして編む・織る/さまざまなテクスチャー/千年の長寿性
□紙の基礎知識
和紙と原料/和紙ができるまで/和紙と洋紙/起源と伝播
□衣食住遊 暮らしを彩る紙
住|八面六臂の働き者
衣|まとい携帯する
食|量産できる身近な素材
遊|豊かな表情を愛でる
和紙の魅力と可能性 関正純(高知県立紙産業技術センター所長)
手漉き和紙の用と美 増田勝彦(和紙文化研究会副会長)
撮影=佐治康生